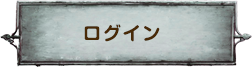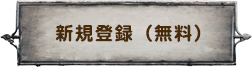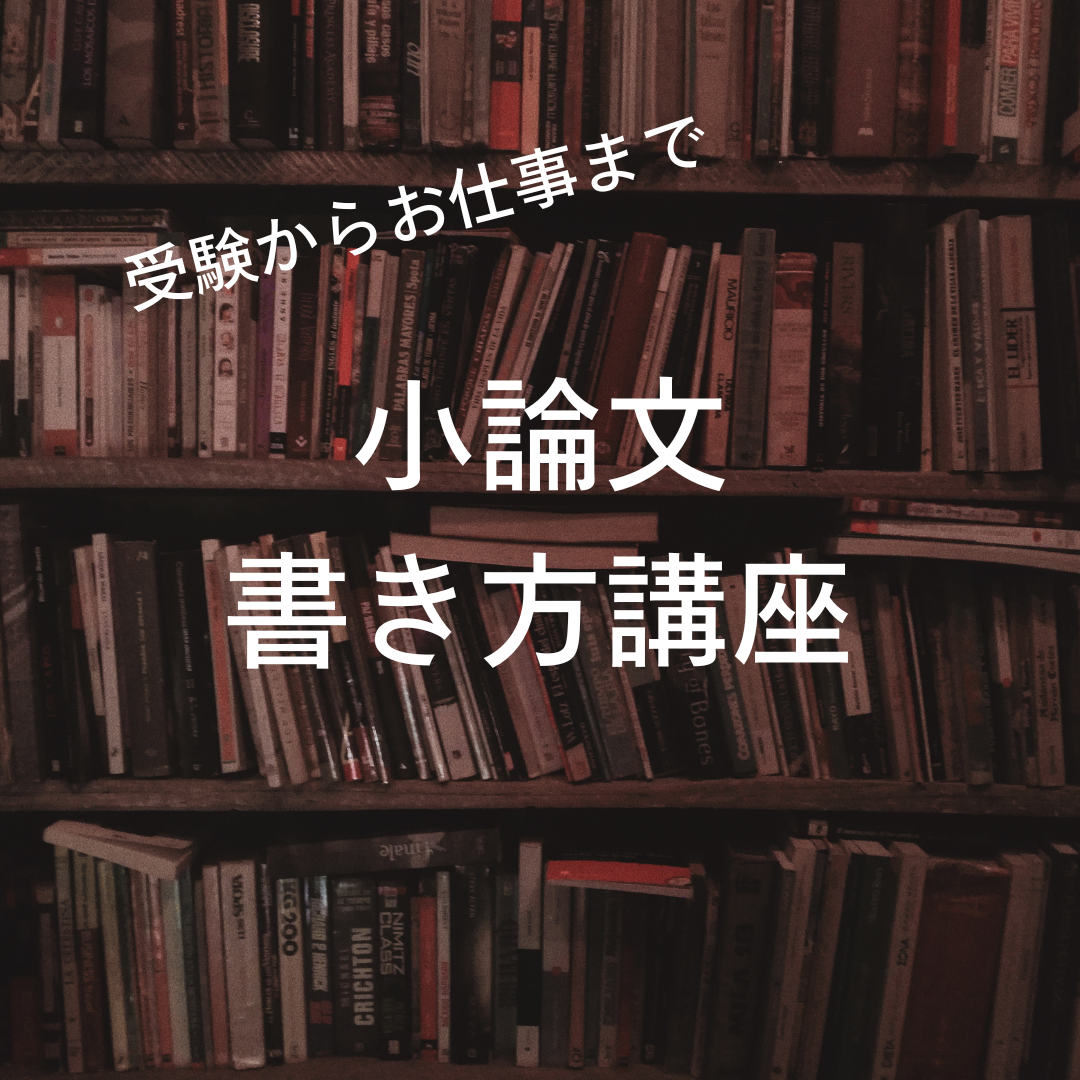こんにちは!おもしろアカデミー講師の「ともひと」です!
国語や小論文を中心に教えています。
今回はタイトルの通り、「小論文」の書き方を簡単にレクチャーさせて頂きますね。
まずは、そもそも小論文とは一体なんかのか?そこからお話させて頂きます。
●小論文とは?
簡単にいうと、次の特徴があります。
①与えられた文章や資料をもとに、設問に対して答える。
②自分の意見を根拠を示しつつ論理的に述べなければならない。
③「序論・本論・結論」などの、ある程度決まった文章の型が存在する。
いかがでしょうか?
よく皆様が小学校などで書かされてきた「作文」は、「自分が感じたことを自由に書く」ものですが、それとは違うということです。
また、小論文は文部科学省による新学習指導要領において育成に重点が置かれている
「思考力・判断力・表現力」をはかる上で非常に効果的なので、
中学・高校・大学等の入試においても多くの学校で出題されていますが、
大学に入学した後に書くレポートでも大事ですし、社会人になっても、
企画書や昇進試験など幅広い機会で書くことがあります。
そして、「論理的に自分の意見を文章化する」ことは、
思考の整理にも繋がるので、是非この機会に学習してみて下さい!
●小論文を書く手順
では具体的にどのように小論文を書いていけば良いのでしょうか?
方法論は色々ありますが、私は次の流れが理想的だと考えます。
①設問を把握する
②文章構成を考える(序論・本論・結論を意識)
③文の繋がりを意識して書き出す
④段落ごとに内容をチェックしながら、指定字数の9割を埋められるように書き進める
一つ一つ見ていきましょう。
まず①ですが、小論文は「設問の要求に答える」ことが必要です。
いくら論理的な文章を書いても「これって聞かれていることに答えてないね」となってしまっては、読み手に評価されません。
次の問題を御覧下さい。
【問】
人工知能AI研究の進歩により、将来様々な分野でのAI活用が期待されています。
最近の社会情勢を踏まえて、十年後の社会ではどのようにAIが利用されているのか、
あなたの予想・考えを600字以上800字以内で述べなさい。
(東京情報大学総合情報学部)
例えばこの問題の場合、
「最近の社会情勢を踏まえて」
「十年後の社会ではどのようにAIが活用されているのか」
「あなたの予想・考えを」
「600字以上800字以内で」
述べるという、4つのポイントがあります。
これをしっかり捉えることが、「設問を把握する」ということです。
漠然とAIについて思ったことを書けばよいわけではないのですね。
次に②の「文章構成を考える」です。これがとても大切なのです。
小論文に限らず、文章を書くのが苦手な人というのは、「とりあえず思いついたことから書いていく」ため、
後半になって文章のバランスがとれなくなり、結局全体的にちぐはぐな文章になってしまうのです。
設問の要求が理解できたら、文書の構成をまず考えましょう。
その際によく使われるのが前述した「序論・本論・結論」です。
それぞれ次のようになります。
序論……文章の最初に来る。文章のテーマを提示し、これから何を書くかを明確にする。
本論……序論で示したテーマに対し、自分の意見を論理的に述べる。小論文の核であり、ここの文章展開が大事。
結論……テーマに対する結論を最後に端的に述べる。
実際に書き出す前に、それぞれの部分で何を書くか、何文字位書くか、そして本論をどのような展開で書くかを先に考えましょう。
簡単なメモ書きにしてみてもいいでしょう。
例えば先ほどの東京情報大学の入試問題を例にすると、次の様な構成が良いと思います。
序論……最近の社会情勢の中でどのようにAIが利用されているかを示し、AIの社会の中での重要性に触れる(200文字程度)。
本論……序論を踏まえて、十年後の社会でのAIの活用例について、自分の予想を述べ、
「なぜそのように活用されるのか」の理由を説明する(400文字程度)。
結論……「以上のように私は十年後の社会では~のようにAIが利用されていると考える」という形で、
設問の要求に合致させる形で文章をまとめる(100文字程度)。
さて、文章構成が決まったら、いよいよ書き出します。
ただし、小論文を書き慣れていない人が特に陥りがちなミスなのですが、「文と文の繋がり」がおかしくなってしまうことが多いのです。
したがって、③「文の繋がりを意識して書き出す」ことが大事です。
一文の文頭と文末が正しく繋がっているか(「なぜなら」から始まったら「から・ので」で閉じているか等)、
次の文は前の文と正しく繋がっているか、これらを文ごとに確認しながら書き進めることをお薦めします。
そして④ですが、一つの段落を書いたあたりで逐一内容をチェックしていくことをお薦めします。
一気に全部書き上げた後に文章をチェックして、文章の最初の段落に大きなミスが見つかった場合、
文書を全部消して最初から書き直すことになってしまいかねません。
またよくあるミスですが、文章の最後近くまで書いて指定字数を大幅に超過してしまいそうな場合、
もしくは指定字数に全然足りない場合に、最終段落の内容をその場しのぎで修正して
なんとか文字数に間に合わせようとすることによって、文章全体のバランスが悪くなってしまうことがあります。
これらは書く前に構成をしっかり練って、書きながらも細かに内容をチェックしていけば防げるミスですので、注意しましょう。
●小論文を書く時のルール・注意点
さて、小論文を書く流れは御理解頂けたでしょうか?
もちろん、手順が分かったからといって実際すぐに完璧な文章が書けるようにはならないでしょう。
また、書きはしたものの本当にこれでいいのか?正しい小論文になっているのかという疑問をお持ちになる方も多いと思います。
そこで、実際に小論文を書く際に気をつけてもらいたいルールや注意点を以下に記載します。
①基本的には「です・ます」調ではなく、「である調」
(面接や志望理由書等と違って、一人の論者として自説を展開する立場なので、である調が一般的です。
ただ、場所によってはです・ます調を推奨するところもあるので注意して下さい)
②書き出し、段落の始めは1マス下げる
③句読点、括弧閉じは行の頭に書かない(前の行の最後のマスに、最後の1文字と一緒に入れてしまいましょう)
④作品名・鍵括弧の中は二重鍵括弧を使う
⑤NGO・ASEANなど、略字の英字は1マスに1文字書く
⑥略字以外の英単語は(縦書きの場合は横倒しにして)1マスに2文字書く
⑦数字は(縦書きの場合は)漢数字で、(横書きの場合は)算用数字で、1マスに2文字書く
⑧流行語・口語・ギャグ等を利用した軽薄な文体はできるだけ避ける
(そういう文は「エッセイ」になってしまいます。あくまで自分の意見を論理的に展開することが大事です)。
⑨文全体の整合性がとれていない・主張が二転三転するような優柔不断な文章にはならないようにする
⑩ことわざ・慣用句・故事成語などの表現はあまり使い過ぎず、
文章の最後のここぞという所で効果的に使う方が文章が締まって良くなる
(自分の知識をひけらかそうとしないで結構です。大事なのは論理的な文章になっているかどうかです)
●終わりに
いかがだったでしょうか?今回御紹介させて頂いたのは、小論文を書く為の基本的なルールや仕組みですので、
実際に書く際には色々なケースがあり、中には一筋縄では行かない場合も多いと思います。
また、いくら書き方を知識として理解しても、実際に書いてみると色々とうまくいかないことも多いでしょう。
その場合、やはり書いたものを誰かに添削してもらったり、個別でアドバイスを貰うことが非常に効果的です。
おもしろアカデミーでは、一人一人の生徒様の御要望に合わせて色々な指導の形を提供させて頂いていますので、
「こういう小論文を書きたいけど、どうすれば良いか教えて!とか
「書いてみたけど、自分では良いかどうか分からないから、ダメな所を指摘して欲しい」というような相談も、遠慮せずにお寄せ下さい。
もちろん私「ともひと」も小論文のプロ講師としていつでも皆様の相談を受け付けております。
是非本日から、「優れた小論文の書き手」への第一歩を踏み出してみて下さいね!